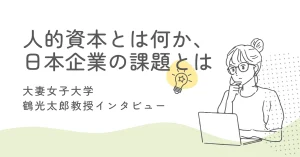人的資本とは何か、日本企業の課題とは――大妻女子大学鶴光太郎教授インタビュー(後編3/3)
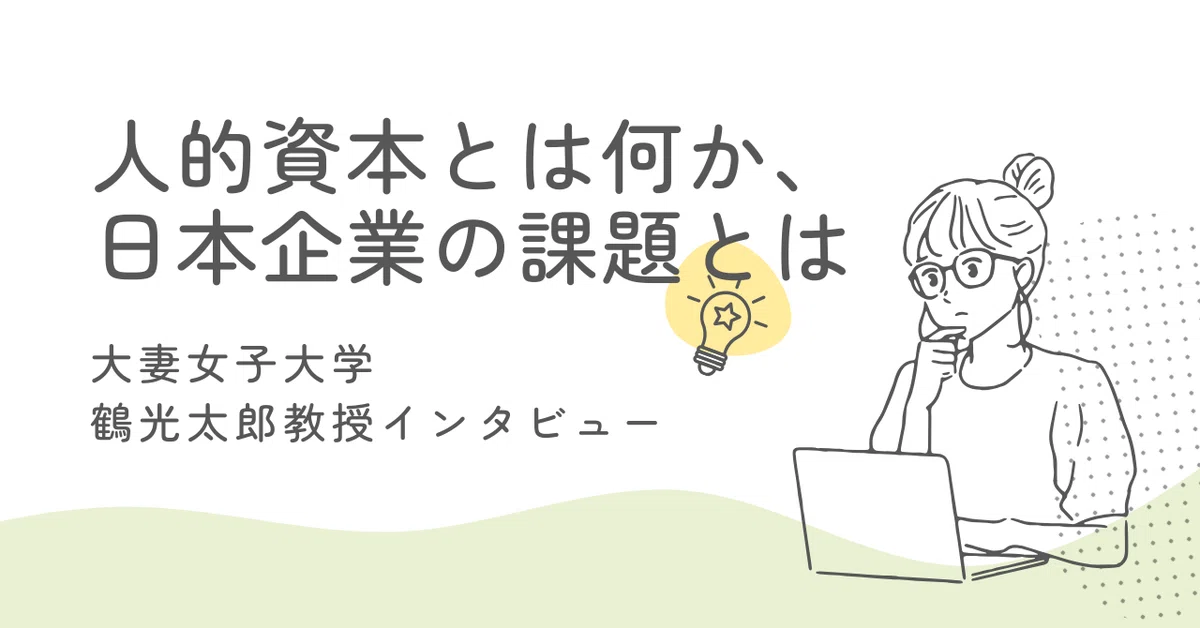
本インタビューでは、企業の働き方改革やリスキリング施策に深く関わってきた鶴光太郎氏に、人的資本経営の考え方やその実践についてお話を伺っています。後編では、リスキリング時代における人材戦略や、「自立・挑戦・成長」が鍵となる人的資本論について、引き続きお話を伺ってまいります
公益財団法人流通経済研究所
上席研究員 石川 友博
研究員 船井 隆
研究員 寺田 奈津美
前編・中編はこちらから👇

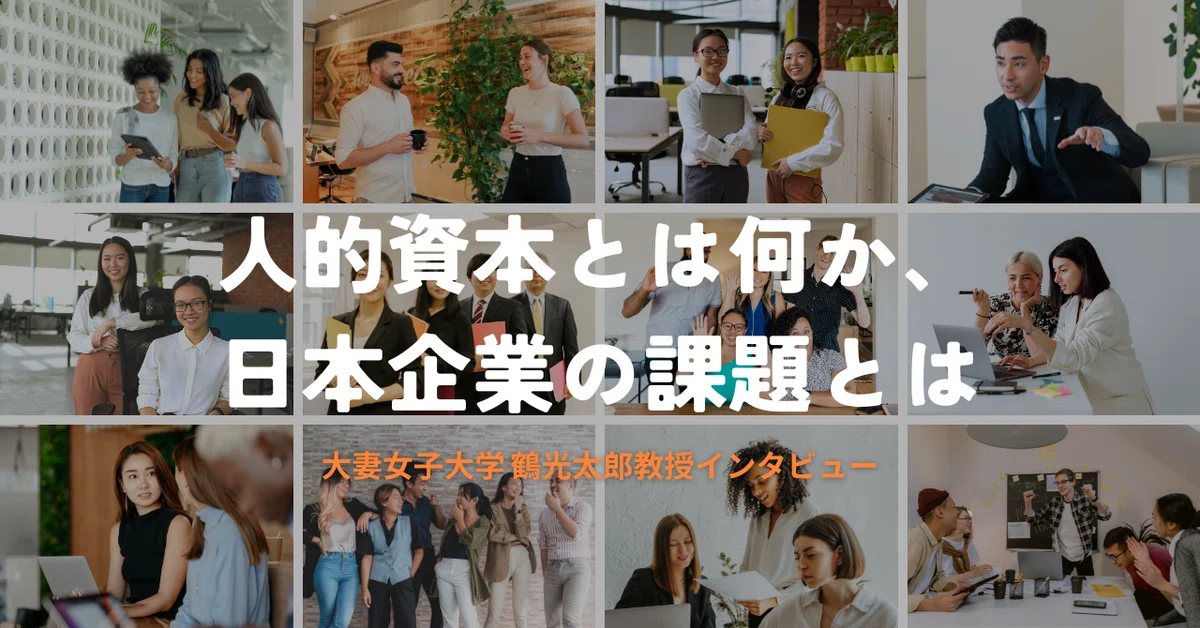
上限規制の先へ──若手育成と創造性を両立させる働き方改革の再構築
――働き方改革の一環として導入された「労働時間の上限規制」についてお伺いします。
長時間労働の是正という点では一定の効果が見られる一方で、R&D部門や若手の成長機会の観点から、画一的な時間規制に対する懸念の声も一部で上がっています。
こうした制度の運用や見直しについて、今後どのような視点が求められるとお考えでしょうか?
はい、この労働時間の上限規制については、私は全体として非常に重要かつ必要なプロセスだったと評価しています。とりわけ運送業、医療、建設業界など長時間労働の常態化が深刻だった業界において、社会的な是正の方向に向かったことは大きな意義があったと思います。
一方で、すべての業種・職種に一律に適用していく中で、やはり現場の実態とのズレが出てきている部分もあります。たとえば、R&D(研究開発)部門などは成果が短期的に現れにくく、辛抱強く取り組むプロセスが必要な領域です。ここで画一的に残業を抑制してしまうと、かえって創造的な仕事が妨げられる恐れもあります。
また、若手社員の成長期において、ある程度の負荷を経験することで得られる学びや飛躍の機会というのは確実にあるわけで、そうした成長機会を失わせてしまっているという指摘も、私自身多く聞いてきました。
さらに、外資系企業などとの人材競争の面でも、「時間」に過度に制限がかかることで、日本企業が不利になっているという声も出てきています。
実は私は、規制改革会議でこのテーマを議論していた当時から、「労働時間の上限規制」と「ホワイトカラーエグゼンプション的な柔軟措置」はセットで導入すべきだと提案していました。つまり、労働時間の規制を全体として整える一方で、業種・職種の特性に応じて適用除外を可能とする、より柔軟な制度設計が必要だという考えです。
ただ当時は、経団連と連合の間でなかなか合意が得られず、結果的に「高度プロフェッショナル制度(コープロ)」のような中途半端な仕組みだけが導入されてしまった。しかも実務上使い勝手が悪いため、ほとんど活用されていないというのが実情です。
その一方で、労働時間の上限規制のほうは政治的な推進力もあって、非常に強力に実装されていった。つまり、本来「両輪」であるべきだった制度が、片輪だけで進んでしまったわけです。
ですので、私は今あらためて、この適用除外や柔軟な働き方を可能にする仕組みを、もう一度再検討する必要があるのではないかと考えています。もちろん、規制をあいまいにするのではなく、明確な基準と厳格な監視体制を前提としたうえで、産業や個人の状況、プロジェクトの特性などに応じた柔軟な対応を認めていく。
そうすることで、働き方改革が本来目指していた「生産性の高い働き方」と「個の成長」の両立に、より近づけるのではないかと考えています。
「手を挙げる学び」が人を育てる──リスキリング時代の人材戦略
――デジタルスキルの習得やリスキリングの取り組みについてお伺いします。
DX対応や生成AIの活用といったテーマが急速に進展する中で、従来型の一律な研修では対応が難しくなってきているという声もあります。
企業が今後、従業員一人ひとりのスキルアップを支援するうえで、どのような考え方や仕組みが重要になるとお考えでしょうか?
はい、まさに今の時代、従来型の一斉研修だけではとても対応しきれないほど、テクノロジーの進化のスピードが速くなっていると感じています。たとえば、少し前まで「プログラミングを学ぶこと」がDX対応だと言われていましたが、今では生成AIなどの登場によって、そのニーズすら大きく変わりつつある。
ですから、「これからの時代はこのスキルが必要です」といった一律の研修メニューを企業側が用意して、従業員に受けさせるというやり方では、もはや時代に追いつけません。
私が強く主張しているのは、多様な研修メニューを用意し、従業員が自分のニーズや関心、業務上の課題に応じて“手を挙げて選べる”ようにするという仕組みです。選択と自律、そしてスピード。これが今、企業に求められている学習支援の基本姿勢です。
実際、先進的な企業ではすでにそうした動きが進んでいます。たとえば、企業内に「●●大学」「●●アカデミー」といった形で自主学習のプラットフォームを設け、オンライン研修などを通じて社員が自由にスキルを選んで学べるようにしている。まさに“手上げ文化”を活かした成長支援の場をつくっているわけですね。
ただ、こうしたスキルはどの企業でも通用する「ポータブルスキル」になりやすく、「そんな研修を提供したら、社員がよその会社に行ってしまうのでは」と不安視する企業もあります。それは確かに、経済学的にも昔から指摘されている通りです。企業が投資しても、それが離職によって回収できないリスクがある。
でも、今は発想を変えるべきなんです。むしろ、そうした機会を提供している企業こそが、「ここにいれば成長できる」「この企業にいる意味がある」と社員に思ってもらえる環境をつくることができる。 その成長機会が魅力となって、優秀な人材の獲得や定着にもつながる。
つまり、「研修を提供すると人が辞める」ではなく、「研修を提供しないと人が来ないし、辞める」という時代に入っているということです。企業が、学ぶ自由や機会を提供できるかどうか。ここが、これからの人材戦略における非常に大きな分岐点になっていると思います。
現場も例外ではない──小売業における人的資本経営の核心とは
――これまで主にオフィスワーカーを念頭に人的資本経営やリスキリングについて伺ってきましたが、小売業などの“現場”で働く従業員においても、同様の視点が求められていると思います。
現場職や接客業といった領域では、人的資本やウェルビーイング、テクノロジーの活用をどのように考えるべきでしょうか?
- はい、これは非常に重要な論点だと思います。私がこれまでお話ししてきた人的資本経営の考え方は、もちろんオフィスワーカーにとっても適用可能な部分が多いですが、現場の仕事、たとえば小売業の接客や販売といった領域においても、決して例外ではありません。
たしかに、接客というのは極めて人間的な、プロフェッショナル性の高い仕事であり、すべてがテクノロジーで代替できるわけではありません。ただ一方で、今のAIやデジタル技術をうまく活用すれば、商品知識の補完やお客様対応の質の平準化といった面で、スキルをカバーできる余地も大きいんですね。
たとえば、生成AIを活用してベテランスタッフの持つ知識や経験をデジタルに再現したり、タブレット端末を通じて接客の際にリアルタイムで情報を提供する。こうした仕組みによって、経験が浅いスタッフでも一定以上のサービス品質を提供できるようになります。これも立派な人的資本経営の一環です。
加えて、私が非常に注目しているのは「売り場ごとのウェルビーイングと業績の関係」です。ある研究では、百貨店などの売り場単位で分析した結果、従業員のウェルビーイングが高い売り場ほど、売上や業績も良いという相関が示されました。
特に興味深かったのは、「平均的なウェルビーイング」だけでなく、「エンゲージメント格差」の影響も明らかになっていた点です。つまり、一部の従業員だけが非常に高い意欲を持っていて、他のメンバーがそうでない場合、結果として売り場全体のパフォーマンスが落ちてしまう。エンゲージメントのバラツキが大きいほど、チームとしての一体感や成果が損なわれるということです。
ですから、現場における人的資本経営では、個々のモチベーションを高めることだけでなく、チーム全体のエンゲージメントの“格差”を是正することも非常に重要なんです。これは管理職や店長クラスのリーダーシップのあり方とも深く関わるテーマです。
また、小売業の現場はそもそも「ジョブ型的」な業務構造になっている部分が多くあります。職務が比較的明確であり、それぞれの業務に必要なスキルや成果も見えやすい。だからこそ、その現場における人的資本の価値をどう最大化していくか、という視点がますます重要になってくると思います。
結論としては、小売業のような現業部門においては、以下の2つが、これからの人的資本経営における大きな柱になっていくと感じています。- テクノロジーによるスキル補完・標準化
- 売り場単位でのエンゲージメント・ウェルビーイングの強化と格差是正
「自立・挑戦・成長」が鍵──若手が企業を選ぶ時代の人的資本論
――お話を伺っていると、人的資本経営の実践が企業の“選ばれる・選ばれない”を大きく分ける時代に入ってきたと感じます。
特に、若手人材の志向や採用スタイルの変化、そして成長機会を与える企業かどうかが極めて重要になっている中で、これからの企業に求められるあり方について、先生はどのようにご覧になっていますか?
はい、まさに今おっしゃった「選ばれる企業と選ばれない企業」の分岐が、いよいよ明確になってきていると私も実感しています。特にこの1~2年で、中途採用、キャリア採用の現場では大きな変化が起きているんですよね。
従来、日本企業では新卒を“まっさらな状態”で一括採用し、その後社内で育てていくメンバーシップ型の人事慣行が主流でした。でも最近は、特に若手から「どこに配属されるか分からない“配属ガチャ”は嫌だ」という声が強くなってきていて、メガバンクのような典型的なメンバーシップ型企業ですら、職種別採用への転換を進めています。
しかも面白いのは、企業側も「ジョブ型」という言葉自体はあえて使わず、実質的にはジョブ型的な制度へと自然に移行しつつあるということです。つまり、企業の側も“選ばれる存在”になるために変化せざるを得なくなっている。私は、これは一種の「地殻変動」だと感じています。
そして、若い人たちは何よりも「この企業で自分は成長できるのか」を非常に重視している。もちろん安定性も大切にしていますが、それ以上に、成長実感のない環境には見切りをつけてしまう。いくらホワイト企業であっても、成長の機会がないならば選ばれなくなってきているんです。
この“成長”というのは、まさに人的資本の蓄積そのものです。自分の専門スキルや経験、非認知スキルを高められる環境かどうか。それを重視する人材が、今は多数派になりつつある。
そして企業側も、従業員の成長がそのまま企業の成長につながっていく“好循環”をいかに構築できるかが問われている。 まさにこの好循環を実現している企業こそが、人的資本経営において最も成果を上げているのです。
では、成長を促すには何が必要か。私は「自立」「挑戦」「成長」――この3つのキーワードが非常に重要だと考えています。
「自立」は、キャリアのオーナーシップを本人が持つということ。「挑戦」は、その自立を前提に自ら手を挙げて新しいことに取り組める環境があること。そして「成長」は、そうした挑戦が本人の能力向上や経験の蓄積につながっていること。
この3つが揃って初めて、人的資本が実際に企業の成果として花開いていく。そして私が見聞きしてきた限り、先進的な企業には例外なく、この3つの要素が含まれていると言っても過言ではありません。
逆に言えば、これが整っていない企業は、若い人材からも見放され、優秀な人材を惹きつけることができなくなっていく。“選ばれない企業”になってしまうんです。
ですから、今まさに企業にとっての転換点が来ていると感じます。人的資本への投資と環境整備を本気で進めなければ、その“差”は今後ますます開いていくことになるでしょう。
出入りのある組織こそ強い──アルムナイ制度が示す未来の雇用像
――人的資本経営の実践が進む中で、従来の日本型雇用、特に「辞める=裏切り」といった発想からの転換も求められているように感じます。
キャリアの流動性や企業間の人材循環について、先生はどのように捉えていらっしゃいますか?
はい、そこは本当に重要な意識転換が求められている部分だと思います。これまでの日本型のメンバーシップ型雇用では、社員は家族のように捉えられ、「辞めること=裏切り」みたいな空気がどうしてもありましたよね。これは、終身雇用や年功序列といった仕組みの副作用とも言えると思います。
でも今の時代はもうそういう感覚では立ち行かなくなっています。辞める人がいれば、また新しく入ってくる人もいる。出入りがあること自体がむしろ自然で、前向きに捉えるべきものなんです。
実際、企業によっては、退職者が再び戻ってきて活躍する「アルムナイ制度」を導入したり、一度外に出てスキルや経験を得た人材を再雇用することを積極的に行っているところも出てきています。これも人的資本の流動性を高めるための非常に良い取り組みだと思います。
そして何より重要なのは、そうした流動性の中でも、組織としての一体感や成長力を保ち続けるということです。人が入れ替わっても、企業としてのビジョンやパーパス、文化がしっかりしていれば、柔軟に対応できる。そういう方向に企業はシフトしていくべきだと思います。
これは決して「日本のやり方を壊すべきだ」という急進的な話ではありません。これまでの日本的な良さを残しつつ、徐々に自然なかたちで変わっていく。今、私が見ている限りでも、もうその動きはすでに始まっていて、案外知らないうちに「随分変わってきたね」と感じられるような段階に来ていると感じます。
つまり、“変革”ではなく“進化”として捉えること。人が循環することをポジティブに受け止め、組織の持続的な成長とつなげていく――それが今、目指すべき方向だと思っています。
まとめ
ここまで、鶴先生から、人的資本とは何か、日本企業の課題とは、についてお話を伺ってきました。ここまでの内容をまとめると、次の3点に整理できます。
1.人的資本を活かすには「スキル獲得 × 自律的キャリア ×組織の支援構造」の三位一体が不可欠
- リスキリングの重要性は認識されているが、メンバーシップ型の雇用慣行や画一的な研修体系のままでは定着しづらく、 ジョブ型的なキャリアの自律性 と スキル活用の場の確保 が必要とされている。
- 特に「自立」「挑戦」「成長」という3つの要素が揃って初めて、人的資本が企業成果に結びつく。
- 学びの選択肢と機会を個人に開放し、“手を挙げる文化”を育むことが、優秀な人材の定着・獲得の鍵になる。
2.ウェルビーイングとエンゲージメントの向上が人的資本の「稼働率」を決定する
- スキルや能力を持っていても、それが発揮されるかは 従業員の心身の状態や意欲に左右される。
- ウェルビーイングを高めるためには「柔軟な働き方」「キャリアの見通し」「共感できるパーパス」など、環境整備が不可欠。
- 特に現場では エンゲージメントの“格差” が業績に影響を与えるため、個々の動機づけだけでなくチーム全体の一体感のマネジメントが重要。
3.雇用と人材観の転換:人的資本の“循環”を前向きに捉える
- 「辞める=裏切り」という旧来の発想から脱却し、人材の出入りをポジティブに捉える意識改革が求められている。
- アルムナイ制度や再雇用制度 を活用し、外で得た経験を再び企業の価値に変える循環構造を築くことが、持続的成長の鍵となる。
- 企業は“人材を囲い込む”から“出入りしながら関係を続ける”方向へシフトし、文化・パーパス・ビジョンの一貫性で人をつなぎとめる戦略が必要。
この3点の示唆を総括すると、日本企業と働く個人の双方にとって、これからの時代に求められるのは「人材を“囲い込む”のではなく、“活かし、育み、つながり続ける”関係への転換」であると言えます。その要点は、以下のように整理できます。
■日本企業が取るべき姿勢:人的資本を「流動性のある資産」として本気で経営に組み込む
- 育てて囲う時代から、育てて動かす・戻す時代へ。 リスキリングやキャリア形成の主体は個人であることを前提に、企業はその意思に応える“環境と仕組み”を提供する役割に徹するべき。
- ウェルビーイングとエンゲージメントは“成果を支えるインフラ”。 心身の健康、意欲、組織文化への共感なくして、人的資本の活用は成立しない。
- “辞めること”を恐れず、“戻ってこられる関係”を築く。 組織の一体感を支えるのは、同一の所属期間ではなく、共有されたビジョン・文化・パーパスである。
■働く個人が目指すべき姿勢:キャリアのオーナーシップを持ち、“学び続け、動き続ける”
- 企業に委ねるのではなく、自らのスキルと価値を自律的に高めていく。
- 「手を挙げる」「選び取る」「試してみる」行動が、成長の起点になる。
- 一つの企業だけでキャリアを完結させる時代は終わり。キャリアは企業との“継続的な関係性”の中で磨かれていく。
人的資本を「囲い込む」のではなく、「育て、活かし、つながり続ける」関係へ――組織も個人も、変化を前提に成長をデザインする時代に変化しなければならないと強く意識させられました。
鶴先生、誠に有難うございました!