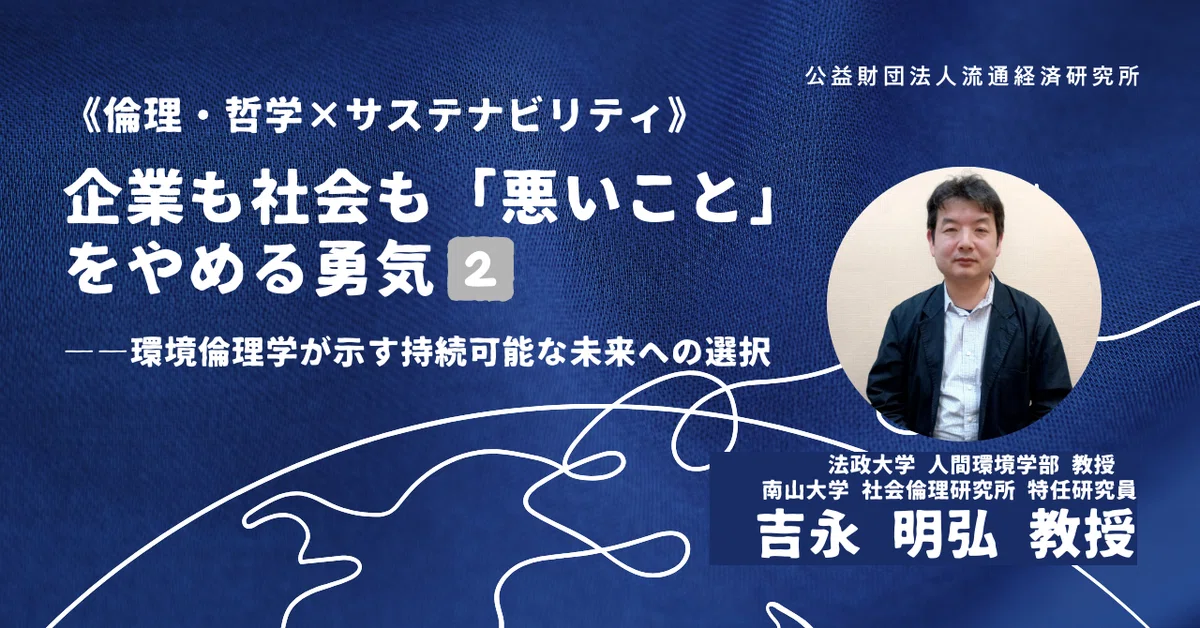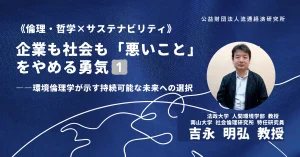《倫理・哲学×サステナビリティ》企業も社会も「悪いこと」をやめる勇気――環境倫理学が示す持続可能な未来への選択(1)
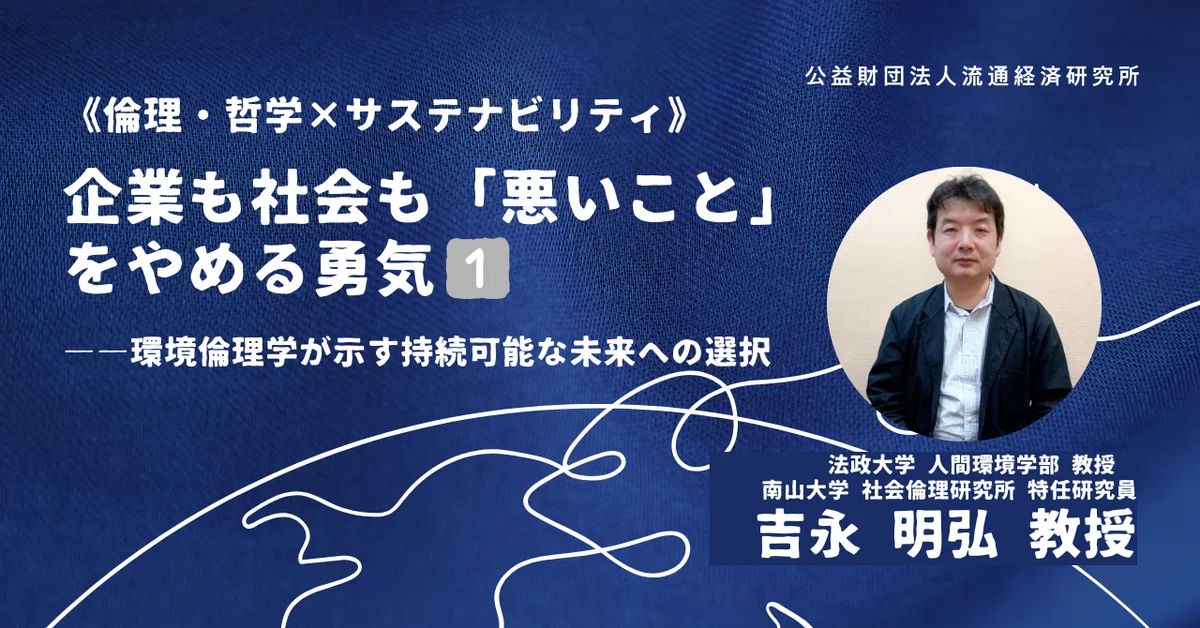
「正解のない時代」に、あなたはどう判断しますか?
気候変動、格差拡大、地政学リスク、パンデミック――私たちは今、予測不能で不確実な時代を生きています。かつての常識や成功法則が通用しない今、企業やビジネスパーソンには、これまで以上に本質を見極める力が求められています。とりわけ、生成AIの登場により「正解を知っているかどうか」ではなく、「自分なりにどう考え、どう行動するか」という本質的な思考力が問われるようになってきました。
そして、イノベーションの起点もまた、「常識を疑い、問い直す」ところにあるはずです。こうした時代に必要なのは、実は“倫理”や“哲学”といった、一見ビジネスと無縁に見える思考の武器なのです。
本記事では、環境倫理学の研究者の吉永明弘先生にお話をうかがい、「どのような企業が倫理的といえるのか」「経済成長と持続可能性の両立は可能か」など、現代ビジネスが直面する本質的な問いを掘り下げます。哲学的思考をビジネスに活かすヒントを得たい方にとって、有益な視点を提供できるはずです。
変化の激しい社会で、判断力・創造力を鍛えたいビジネスリーダー、企画職、サステナビリティ担当の皆さま必読です。
公益財団法人流通経済研究所
研究員 寺田 奈津美
1. 環境倫理学とは何か

南山大学 社会倫理研究所 特任研究員 吉永 明弘先生
寺田:環境倫理学とはどういう学問領域なのか、その概要についてご紹介いただけますか?
吉永先生:はい。環境倫理学は、その名の通り「倫理学」に属する分野で、倫理学はもともと哲学の一部として位置づけられています。その中でも、20世紀後半から発展してきた「応用倫理学」の一分野として登場しました。
応用倫理学には、たとえば生命倫理や情報倫理(最近ではITやAIに関わる倫理など)がありますが、これらはいずれも、科学技術の発展によって新たに生じた課題に対して、倫理学の立場から応答しようとする試みです。環境倫理学もそのひとつで、科学技術や産業活動によって引き起こされた環境問題に対し、倫理的にどのように向き合うかを考える比較的新しい学問です。1970年代に始まった分野なので、まだ50年ほどの歴史しかありません。
日本では1990年代に本格的に導入されました。アメリカで環境倫理学が生まれた当初は、広大な自然を背景に、「自然をどのように守っていくか」「自然そのものにどのような価値があるのか」といった問いが重視されていました。
一方で、日本で導入された90年代以降は、ちょうど地球温暖化などのグローバルな環境問題が社会的に注目され始めた時期でもありました。そのため、日本における環境倫理学は、自然の保護だけでなく、「持続可能性」や「将来世代への責任(世代間倫理)」といったテーマにも重点が置かれるようになりました。
このように、アメリカで始まった環境倫理学と、日本で展開された環境倫理学とでは、扱われる課題や注目される焦点に違いがあります。こうした違いは、それぞれの時代背景や社会的文脈の違いによって生まれたものです。
環境倫理学は一般に「自然の価値」や「自然の権利」を扱う学問として紹介されることが多いですが、それにとどまりません。「持続可能性」や「将来世代への倫理的責任」、さらには「地域環境(ローカルな課題)」をどのように捉えるかといった視点も含まれており、グローバルな問題意識とローカルな問題意識、そして自然との関係性をめぐる価値観が交差する、多層的で広がりのある学問領域です。
私が授業でこの分野を説明する際には、「アメリカと日本」「1970年代と1990年代」「グローバルとローカル」という三つの軸をもとに、環境倫理学の成り立ちと展開の特徴を整理するようにしています。
2. 環境倫理学の三つの基本主張
寺田:ありがとうございます。続いての質問ですが、著書の中に「環境倫理は個人の倫理というよりも、社会の倫理である」というお話がありました。また、環境倫理には「三つの基本的主張」があるとも書かれていました。その点について、詳しく教えていただけますでしょうか。
吉永先生:はい。現在では高校の倫理の教科書にも掲載されているのですが、日本における環境倫理の「三つの基本主張」は、哲学者・倫理学者の加藤尚武氏によって提唱されたものです。
その三つとは、
①自然の権利
②世代間倫理
③地球全体主義
です。
まず、「自然の権利」という考え方を本気で取り入れようとすると、現行の人権中心の法体系では対応しきれず、法律そのものを根本から見直す必要が出てきます。自然にも権利があると考えるなら、人間だけを中心とした制度では限界がある、ということになります。
次に「世代間倫理」ですが、これは現在の社会の意思決定のあり方を問い直すものです。たとえば国会や学校の学級会のような場では、基本的に「今ここにいる人」が意思決定をしますが、環境問題では「まだ生まれていない人」や「将来の世代」のことまで考慮しなければなりません。そうなると、「誰が意思決定に参加するのか」「どのように意思決定を行うのか」といった、仕組みそのものを再設計する必要が出てきます。
最後の「地球全体主義」は、おそらく最も直感的に理解しやすいテーマだと思います。これまでは「資源がなくなったら、他の場所から調達すればいい」「新しい技術で解決できる」といった発想が主流でしたが、地球全体で見たときに、資源や空間には明確な限界があります。そうした限界のなかで、どう経済活動を組み立て直すのか。つまり、もはや従来の経済成長至上主義ではやっていけないという認識が必要です。
このように、環境倫理の三つの主張はいずれも、個人の心がけや行動のレベルを超えて、法制度や政治、経済など、社会全体の仕組みそのものを見直す必要があることを示しています。だからこそ、「環境倫理は社会の倫理である」と言われるのです。
3. <深堀り>未来世代への責任と世代間倫理
寺田:ありがとうございます。では、その三つの基本主張のうち「世代間倫理」について、もう少し詳しくお聞かせください。環境問題においては、具体的にどのような議論がなされているのでしょうか?
吉永先生:典型的な例は、放射性廃棄物の処理問題です。世代間倫理の最大の特徴は、「今ここにいる世代」――たとえば赤ちゃんや子どもたちのことだけでなく、まだ生まれていない、遠い将来の世代のことまで考えるという点にあります。
近い将来であれば、「そのうち新しい技術が開発されて問題が解決するだろう」と期待することもできますが、100年後、1000年後のような遠い未来にまで責任を持てるかというと、それは簡単ではありません。そのときの人類がどんな姿であるから、私たちには分かりません。
とはいえ、私たちと同じように生物として存在している限り、「何が毒であるか」という基本的な生理は、1000年経っても大きくは変わらないでしょう。そう考えると、「将来の人類は放射性物質に強くなっているはずだ」というような発想は、あまりにも無責任です。将来の世代にまで影響を及ぼす放射性廃棄物を、今の世代がこれほど大量に出してしまっていいのか、という問いが、世代間倫理の重要な問題のひとつです。
もう一つの例として、花粉症も挙げられます。花粉症の原因はいくつかありますが、たとえば過去に大量に杉を植えた政策の影響によって、現在の私たちが苦しんでいる側面があります。すでに亡くなった世代の行動が、現代の健康や生活に影響を及ぼしているわけです。これと同様に、今私たちがしていることが、将来世代に何らかの形で影響を与えるというのは、ほぼ確実だといえるでしょう。
また、地球温暖化に関する「ジオエンジニアリング(気候工学)」の議論もあります。たとえば、大気中のCO2の排出がなかなか減らないため、空気中のCO2を回収・貯留したり、成層圏に微粒子を散布して太陽光を反射させたりといった、気候を人為的にコントロールする技術が検討されています。
これらの技術には、たしかに一定の効果があるとされていますが、問題は「一度始めるとやめられない」という点です。たとえば、成層圏に粒子を散布して冷却効果が得られたとしても、それをやめればすぐに温暖化が進行してしまうと言われています。つまり、こうした技術を導入した瞬間から、それは現在の世代だけで完結する問題ではなく、将来世代に継続する「責任と義務」を押し付けることになるのです。
このように、世代間倫理は「子どもたちや孫のために」という道徳的なスローガンのように見えるかもしれませんが、実際には「100年後」「1000年後」、あるいは「数万年後」にまで影響を及ぼす技術や廃棄物を抱えてしまっている私たちの現実を直視し、その責任のあり方を問う必要があるという、非常に重たい課題を含んでいるのです。
寺田:新しい技術を導入する際や、今後の社会の方向性を考えるうえで、まさに不可欠な視点なのですね。
吉永先生:そう思います。先ほどお話しした三つの主張――「自然の権利=自然や動物にも権利がある」「世代間倫理=未来の世代のことを考えよう」「地球全体主義=地球には限りがある」という考え方は、どれも言われれば納得のいくものですよね。
ところが現実には、動物に危害を加えたり、自然環境を破壊して土地を奪ったり、「地球は無限である」という前提に立って経済成長を優先するような開発が、いまだに行われているわけです。つまり、私たちはその納得できる価値観を、実際には裏切っている。そのことを、もう一度立ち止まって考える必要があるのではないでしょうか。
4. 個人の努力と社会の構造――温暖化が止められない理由
寺田:先生は、著書の中で、「地球温暖化をなぜ止められないのか」という問いに対して、〈世界的に産業界には甘く、消費者に責任を押しつける政策が続いている〉と指摘されています。この点について、詳しくお聞かせいただけますか?
吉永先生:はい。まず温暖化の話に入る前に、公害問題を例にとってみたいと思います。たとえば水が汚染されたとき、私たちは自衛のために浄水器を買ったりしますよね。でも、なぜ汚染の原因をつくった側ではなく、被害を受けている側がその負担を強いられなければならないのか、という疑問があります。花粉症でも同じで、空気清浄機などを買って個人で対策しているわけですが、本来は過去に過剰な植林をした政策など、原因となった行為があるはずです。
そして、温暖化対策においても同様の構図があります。私たちは「電気をこまめに消しましょう」「省エネしましょう」といった啓発を受けますが、個人の努力で削減できるCO2の量には限界があります。実際には、都庁や大学のような大口の排出元が削減に取り組むことで、一気に効果が出る可能性もある。それにもかかわらず、そうした対策が後回しにされ、まずは個人に努力を求めるのは、効果の面でも公平性の面でも疑問が残ります。
ですから、やはり産業界、特に大規模な生産活動を行っている企業こそが、優先的に責任を果たすべきではないかと考えています。
寺田:日本では、個人一人ひとりに省エネ行動を求めることが喧伝され、それがあまりにも当然のように受け入れられている雰囲気がありますよね。でも、先生は、企業の行動を促したり、社会的な運動を起こしたりするような選択肢がもっと認められてもいいのではないか、と指摘されています。この点について、どうお考えでしょうか?
吉永先生:おっしゃるとおりです。学生と話をしていても、似たような反応があります。たとえば極端な例ですが、CO2を減らしたいなら戦闘機を削減するというのも一つの選択肢になるわけですよね。そのほうが家庭の省エネよりも効果が大きいはずです。
でも、そういう話にはなかなかならず、「家庭でできることを考えましょう」という方向にばかり議論が誘導されてしまう。そして、一人ひとりの行動には限界があると授業で言うと、環境問題に熱心な学生ほど、自分がコツコツ続けてきた省エネ行動が否定されたように感じてしまう。そうなると、自分自身の価値や行動が傷つけられたように受け止めるのですね。
環境に関心がある人ほど、「一人一人の努力は無駄だ」と受け止めてしまい、強い拒否感を抱く傾向があります。ただ、現実には本当に環境を守ろうとするなら、大きな排出源、つまり社会の仕組みや産業構造を変えていかなければ、大きな効果は期待できない。そこを直視する必要があると思います。
寺田:学生が否定されたように感じる、というのは新鮮な視点でした。それだけ、「一人ひとりの心がけ」が当然視されているんですね。私自身も、産業界や法律のほうが変わったほうがインパクト大きいと思っているのに、それを口にしづらい雰囲気を感じていて……。今日初めて、それをはっきりと言ってくださる方に出会った気がして、ハッとしました。
吉永先生:そう感じていただけたならよかったです。環境倫理関連の研究者の中では、たとえば平川秀幸氏や井上有一氏などが、私と同じような主張をされています。「一人一人の努力も大事だけど、それだけでは十分ではない。社会全体を動かしていくことが必要だ」ということですね。
5. 倫理的な企業活動とは――悪いことをやめる決断を評価する文化へ
寺田:国の政策として企業に消費者啓発を促すようなものもありますが、その点で、吉永先生にとって「倫理的な企業活動」とはどのようなものだとお考えですか?また、具体的な企業の例があれば教えていただけますか?
吉永先生:そうですね。まず前提として、企業の前に政治が変わらなければならないというのが私の立場です。つまり、法律の整備や、必要に応じた規制の強化といった取り組みがもっとなされるべきだと思っています。
そのうえで、「一人ひとりが何をするか」を考えると、多くの日本人は会社員として社会に所属していますよね。ということは、会社そのものが変われば、社員一人ひとりの行動も自然と変わっていく。だからこそ、企業にアプローチしていくというのは、とても重要なことだと考えています。
では、具体的に「倫理的な企業活動」とはどのようなものかというと、以前、環境活動家の田中優氏が「良いことをしようと思う前に、悪いことをやめることの方が重要だ」と述べており、この考え方にはとても腑に落ちました。
私としては、「これをすれば倫理的な企業になれる」というものはないのですが、まずは企業が、現在の自社の事業や活動を見直し、そこに環境負荷や人権侵害につながるような行為がないかを総点検する。そのうえで、問題が見つかった場合は、勇気を持ってやめていく。そうした姿勢をもった企業こそが、倫理的な企業といえるのではないかと思います。
最近では、環境に配慮した企業活動に対して、投資家が企業評価を行うようになっていますよね。例えば、植林活動をしている企業や、環境にやさしい製品を開発している企業に投資が集まるというのは、よく理解できます。
ただ私がもっと評価されるべきだと思うのは、「これまではこういうことをしていたが、環境への負荷が高いと判断し、やめることにしました」といった姿勢です。一般的には「やめました」と言うとマイナス評価になりがちですが、それをむしろプラスに評価する文化が必要だと思っています。
これは投資家に限らず、一般の人々も同様で、「この事業はやめたほうがいいと判断して中止した。それは立派な判断だ」と前向きに評価されるようにならないと、企業としてもやめることに対するインセンティブが生まれません。
大学などもそうですが、一度始めたプロジェクトは途中でやめにくいものです。やめると評価が下がってしまうからです。これは個人でも部署でも同じです。特に行政では、自治体でも国でも「こんな道路、必要ないのでは?」と思われる道路がつくられてしまう。なぜかというと、一度計画が決まると、それを実行しないといけないという構造になっているからです。途中でやめると、内部的にも外部的にも批判されてしまう。だからやめるという選択肢がとりにくいのです。
無駄な道路を減らすには、もちろん「この道路はおかしい」と反対運動をするのも一つの方法です。でももう一つ大事なのは、「やめた」という判断をした企業や部署、役所に対して、社会全体が「よくやめましたね」と称賛する文化をつくることです。そういった文化が必要だと私は思います。
寺田:ということは、たとえ環境によくないと分かっていても、企業側が「やめる」という決断を避ける傾向がある。そのため環境問題の改善が進まない。だからこそ、悪いことをやめるという選択を積極的に評価する文化が求められる、ということですね。
吉永先生:はい、そうです。もう一つの要因として、「損切りができない」という経済的な側面があります。たとえば「ここまで投資したのだから、最後までやらないと元が取れない」といったサンクコストの考え方ですね。けれども、損切りせずに続けることで、かえって経済的にも大きな損失になる可能性があるわけです。
さらに、社会的な評価も大きな壁になっています。大学でも「○カ年計画」といったものを設定すると、それを完遂することが評価され、途中で中止すれば「失敗した」と見なされる。そういう風潮がありますよね。これは大学に限らず、どのような組織にも共通している文化だと思います。官庁などでは、特にその傾向が強く、やめるにやめられない状況がたくさんあるのではないでしょうか。
((1)終わり)
(2)はこちら👇